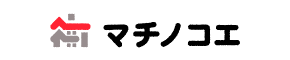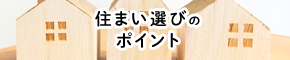西新井大師

出典:「西新井エリアガイド」
http://tokyo.itot.jp/nishiarai/28
正式名は五智山遍照院總持寺。「弘法大師」の諡号で知られる空海を祖とする、真言宗豊山派の名刹だ。西新井の名は826(天長3)年、巡礼中の空海が立ち寄って祈祷を行った際、お堂の西側にあった枯れ井戸から水が湧き出たという説に由来する。この清らかな水は、病をまたたく間に治したほどの霊験あらたかなものであり、ここから西新井大師は厄よけ・開運に利益があるとされている。
「関東の高野山」とも称される関東厄除け三大師の一つです。お参りに行くなら、名物の「草だんご」は外せません。山門前にある中田屋と清水屋には、いつも多くの人で賑わっています。
川崎大師

出典:「鈴木町エリアガイド」
http://kanagawa.itot.jp/suzukicho/45
開創は1128(大治3)年。もろもろの災厄を消除する厄除大師で、大本堂内には御本尊厄除弘法大師を中心に、不動明王や愛染明王などの諸仏が奉安されている。毎年夏には風鈴市が開かれ、各地の様々な風鈴の音の共演が境内で繰り広げられる。夏の風物詩として、関東近郊はもとより全国の人々に親しまれている。
参拝のついでに「仲見世通り」での買い物も楽しみたいですね。川崎大師の名物の「せき止め飴」と「厄除けだるま」。また、京急はもともと川崎大師への参拝客輸送を目的に設立されたため、「川崎大師」駅近くには「京浜急行発祥の地記念碑」もあります。
明治神宮
出典:「渋谷駐車場ガイド」
http://area.repark.jp/rp-shibuya/33
明治天皇と昭憲皇太后を御祭神とする神社。70ヘクタールに及ぶ境内には、本殿を中心に厄除や七五三などの祈願を行う神楽殿、宝物を陳列する宝物殿などがある。
言わずと知れた、初詣の参拝客数日本一の神社です。ブランドショップなどが立ち並ぶ表参道も、もともとは明治神宮の造営に合わせて整備された道です。
大國魂神社

出典:「府中エリアガイド」
http://tokyo.itot.jp/fuchu/157
東京、埼玉、神奈川の北東部にまで及ぶかつての武蔵国の守り神をお祀りしている「大國魂神社(おおくにたまじんじゃ)」。創建より1,900余年を迎える、都内で最も古い歴史のある神社のひとつで、“武蔵総社(むさしそうしゃ)”として親しまれ多くの参拝者が訪れます。
645(大化元)年の「大化の改新」により、国の政務を執り行う国府がおかれた場所でもあります。都指定無形民俗文化財となっている「くらやみ祭」も有名ですね。
靖國神社

出典:「九段北時間」
http://tokyo.itot.jp/kudankita/122
明治天皇の思し召しによって創建された「東京招魂社」が始まりで、1879(明治12)年に「靖國神社」と改称された。「靖國神社」には幕末の志士達をはじめ、明治以降の戦争・事変で国を守るために尊い生命を捧げられた246万6千余柱の神霊(みたま)が祀られている。
境内にはソメイヨシノやヤマザクラなど約500本の桜があり、初詣だけでなく、春にも多くの参拝客が訪れます。テレビでもおなじみの東京の桜開花の基準となる標本木は、靖國神社の境内にあります。

 気になる街の記事検索
気になる街の記事検索
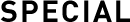 特集記事
特集記事

 お知らせほか
お知らせほか